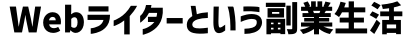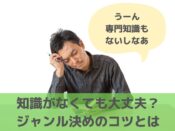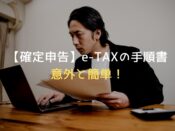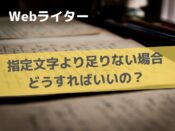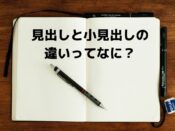Webライターなら知ってて当たり前!見出しと小見出しの違いを解説
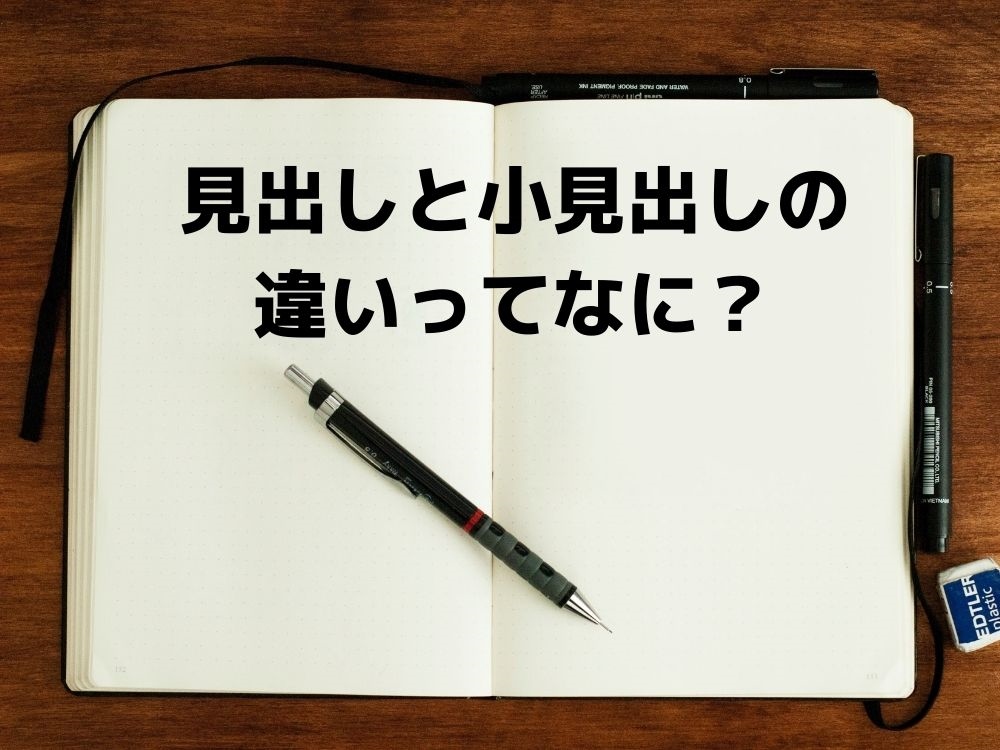
こんにちは!
最近天気が崩れやすくて嫌ですね。
でも涼しくなったので、過ごしやすい季節になって嬉しいです。
今日は見出しに関しての記事です。
見出しってご存じですか?
本で言うところの「章」や「節」の役割を持つのが見出しですね。
当然、Web記事においても見出しってかなり大切です。
見出しのない記事は読者の離脱につながりますし、Google内でサイト構造などの情報を収集するクローラーと呼ばれるシステムからも理解してもらえません。
Webライターに関してであれば、今まで構成案を作ったことがない方が、どのような見出しにすればいいのか迷うなんてこともあるでしょう。
そこで今回は、見出しとはどういったものなのか、その必要性についてご紹介していきます。
Webライターの構成作りで見出しの利用は必須

Webライターの構成作りにおいて、見出しの利用は必須です。
見出しのない構成案を提出したところで絶対にOKはもらえません。
そのため、見出しとはどういった役割を持っているのか、どの部分に設置すればいいのかということをきちんと理解しておく必要があります。
今まで、構成をもらって文字だけを書いていたライターからすれば、少し難しいと感じてしまいますが、そんなに難しいものでもないのでぜひこの記事で理解していってください。
見出しの役割とは
見出しとは、話の内容が変わる個所に設置する、いわゆる仕切り板のようなものです。
例えば、本屋さんに行けばマンガを置いている棚を見ても、「少女マンガコーナー」「少年マンガコーナー」などありますよね。
さらに、マンガのタイトルや出版社によって区切りがあると思います。
そのようなイメージです。
つまり見出しがなければ、どこまでにどのような内容を書いているのか理解しづらいということです。
そうなると、求めている情報がある部分まで上から順に読み続けなければなりません。
かなり非効率だと思いませんか?
例えば、車のオイル交換時期を知りたいだけなのに、ブログ記事を開くと上から、エンジンオイルとはどういったものなのか、その役割を書いている。
その下にやっと交換時期を説明している。
このような状態であれば、記事を開いてすぐに目的の情報が書かれている場所にたどり着けませんよね。
しかし、見出しがあったらどうでしょうか?
見出しがあれば、「オイル交換の時期とは?」このような見出しがある部分までスクロールして、すぐに知りたい情報を得られます。
そのため、Web記事に見出しは必須なのです。
見出しと小見出しの違いとは?
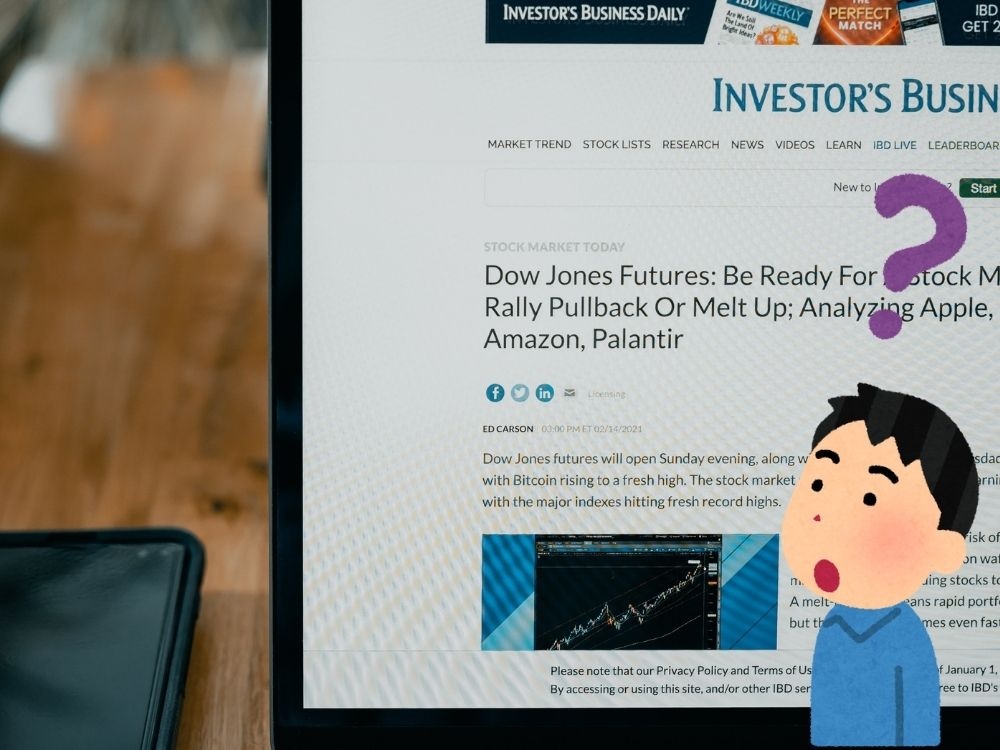
見出しの呼び名は複数あります。
大見出しや小見出し、中見出しと呼ばれたりh2タグやh3タグと呼ばれたりするんですよね。
また、大見出しをh2としているのか、タイトルであるh1としているのかというのも、人によって違います。
ぼく自身は
・見出し⇒h2
・小見出し⇒h3
としているので、この記事ではこのルールで書いていきます。
ときにはh2を大見出しと呼んだりもしますが、今回は見出しと表記しますね。
見出しは記事内の小さなタイトル(h2タグ)
見出しとは記事内にある小さなタイトルです。
見出しとして見るのであれば、h2が最も大きな見出しになります。
大きく話が変わる部分で使用します。
例えば、メルカリで販売した商品を発送する方法という記事を書いていたとしましょう。
1つ目の見出しで「メルカリでの発送方法は複数ある」というように、発送方法は1種類じゃないんだよって内容を伝えます。
そして、2つ目の見出しで「メルカリでの発送方法」というような見出しを作り、具体的にどこで発送できるのかを説明する。
このような形で見出しを作ります。
これが大きな見出しです。
記事内にこのような区切りがあれば分かりやすくないですか?
自分が読んでみて、どんな見出しがあれば分かりやすいかなって考えながら書いていくといいかもしれません。
小見出しは見出し内の小さなタイトル(h3タグ)
小見出しは、見出し内の小さなタイトルというイメージを持ってもらえればと思います。
見出しを作ったけど、書く内容が多すぎて文章量が増えすぎたときや、見出し内の内容で複数の種類がある場合に使用します。
例えば、先ほどのメルカリでの発送方法に関しての内容を例に挙げると、「メルカリでの発送方法」の下にいくつか小見出しが作れそうです。
メルカリではヤマトと郵便局、この2社と提携しています。
さらに、未定とすることで佐川などからも発送可能です。
これを説明したいのであれば、「メルカリでの発送方法」の下に
・小見出し①「らくらくメルカリ便」(ヤマト運輸)
・小見出し②「ゆうゆうメルカリ便」(郵便)
・小見出し③「未定」
最低でもこの3つの小見出しを作ることができます。
そして、小見出し内に具体的な情報を書いてあげましょう。
さらにもっと小さな見出しとして、h4もありますが、この見出しはあまり使わないので、はじめのうちは覚える必要はありません。
経験を積みながら、使用していく程度で大丈夫です。
見出しがないとSEO的にもアウト!

見出しに関しては、読みやすさの観点だけでなく、見出しを設定しないことはSEO的にもよくないです。
Googleはこのように記載してあります。
「分かりやすい見出しを使用して重要なトピックを示すと、コンテンツの階層が生成され、ユーザーがドキュメント内を移動しやすくなります。」
つまり大切な部分を見出しに設定することで、読者が読みやすくなるよっていっているんですね。
Googleが適切な見出しの作成を奨励しています。
逆に考えると、見出しの作り方が悪かったり、作らなければGoogleからのよい評価は得られないということです。
そのため、見出しを適切に使用するのは、SEO的にも大切なのです。
まとめ

見出しとは、本で例えると「章」や「節」のような役割を持ちます。
Webライティングにおいて、絶対に必要です。
はじめの内は見出し(h2)と小見出し(h3)この2つさえ覚えておけばOK。
重要なポイントで適切に使用するように心がけましょう。
見出しが上手な人は、記事全体のバランスがいいです。
他の人の記事を見るとき、どんな見出しを作っているか意識しながら見てみることをおすすめします。