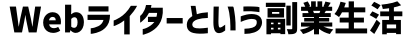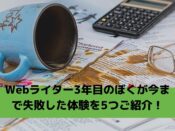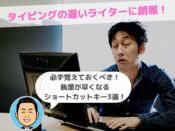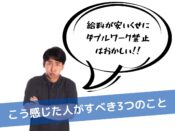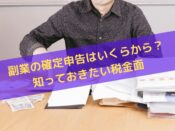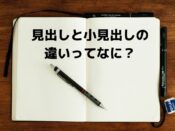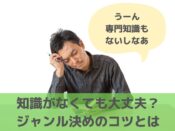Webライターは納期や作業の束縛が多い仕事なのか?実体験を元に徹底解説!
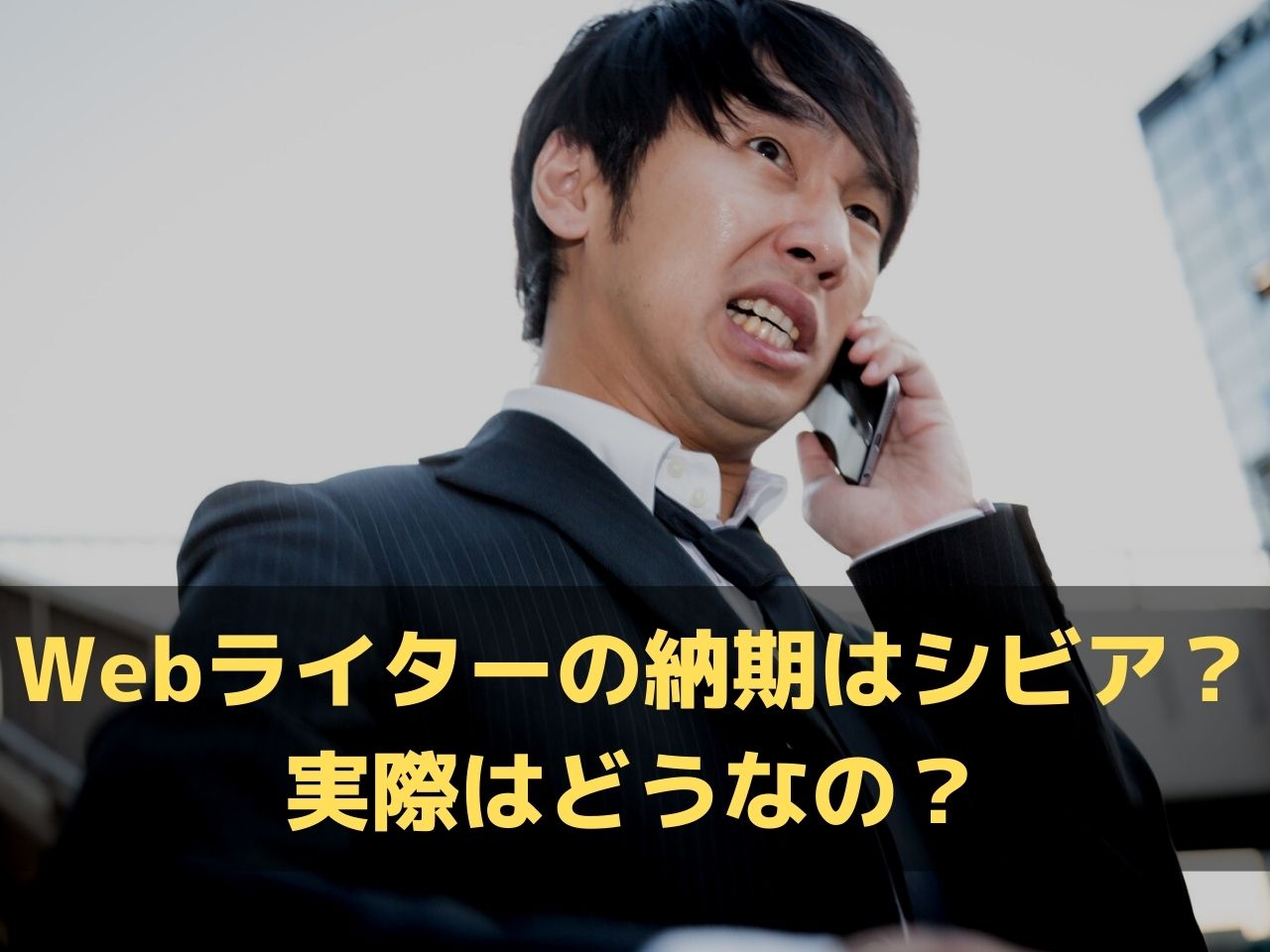
こんにちは!
最近大食い動画にハマっています。
バクバク食べるのを見ると、結構スカッとします(笑)
今日は、Webライターは納期や作業の束縛が多い仕事なのかについて書いていきます。
正直、自分一人で作業するアフィリエイトと比べると、納期もありますし作業のルールなども決められていることが多いので、束縛が多いなと感じる方もいるでしょう。
しかし、慣れてくればそんなに気にならないのも確かです。
また、細かいマニュアルを渡してくる依頼主もいますが、ほとんど何のルールもない人もいます。
そこらへんは依頼主次第かなって思います。
では詳しくお話ししていきます。
Webライターの納期は依頼主によってまちまち

Webライターの納期は依頼主によってまちまちです。
また、納品までの流れも全く違います。
例えば、5月26日に1記事だけ依頼を受けたとしましょう。
依頼主Aさん
「2週間以内に納品してください」
依頼主Bさん
「構成作りを28日まで、記事作成を31日までにお願いします」
このように、同じような依頼内容でも、依頼主によって納品までの流れが大きく変わります。
時間に余裕がなかったり記事作成スピードが遅い、Webライター初心者の方はAさんのような依頼主を見つけるべきだと考えます。
納品までの流れの違いは、文字単価とは全く関係ありません。
納品までのスケジュールが細かいからといって、文字単価が高いわけではないですし、逆に納品までのスケジュールが緩い場合でも文字単価が高いこともあるのです。
納期の平均は1記事1週間程度
依頼主によって大きく変わる納期ですが、平均すると1記事1週間程度だと思います。
1記事に1ヶ月かけてもいいといってくれる依頼主もいます。
逆に、3日で1記事書いてほしいとか、1週間で5記事書いてほしいなんて要望も。
その点は、依頼内容をよく確認して応募するかどうかを決めましょう。
クラウドワークスやランサーズなどで依頼に応募する場合、何日間で何記事書いてほしいのかを依頼内容に記載していることが多いからです。
Webライターを始めたいけど納期が気になる人が意識すべきポイント3選!

ここまでの話を聞いてもまだ、納期が気になる人は以下の3つのポイントを意識してみましょう。
依頼を受ける前に依頼主に相談してみる
依頼主に納期に関して相談してみるのも、方法としては有効です。
先ほど、依頼文に何日間で何記事書いてほしいかという記載があるといいました。
しかし、捕捉として「無理な場合は相談してください」と書いていることも多いです。
そのため応募する際、納期に関して相談してみることをおすすめします。
案外、柔軟に対応してくれる方もいらっしゃいます。
また、納品速度が月によってまちまちなのであれば、月の初めか依頼をもらう際に、あらかじめどの程度で納品できるのかを連絡しておくといいでしょう。
個人アフィリエイターの依頼を受ける
どちらかというと、個人アフィリエイターの依頼の方が納期に関して柔軟です。
企業での依頼の場合、納期に関して柔軟に対応してくれないこともあります。
もちろん、全ての企業さんがそうだとは言いません。
柔軟に対応してくれる企業ももちろんありますし、納期に関してシビアな個人アフィリエイターももちろんいます。
しかし企業の場合、そのサイトで社員を養っていることが多いため、納品が遅れるとどうしても仕事に差し支えてしまいます。
その点、個人アフィリエイターの場合、
- 副業としてアフィリエイトをしている方
- アフィリエイト以外でも収入のある方
このような方がいるため、比較的納期に関して柔軟です。
逆に、たくさん外注を雇っている場合、月1記事の納品でも、補助要員として継続して依頼をくれることも多いのです。
依頼数を最低限に絞る
依頼数を増やせば増やすだけ、納期に間に合わない可能性が高くなります。
そのため、まずは1記事だけというように、最低限、納品できる依頼数に絞るという方法も効果的です。
納期遅れの原因は、執筆速度の予測の甘さに加え、依頼をもらいすぎて手が回らなかったなんて理由も多くあります。
そのため、1記事何日以内に執筆できるという予測ができないのであれば、まず1記事の依頼をもらうことから始めましょう。
1記事であれば、納品当日に完成させることもでき、執筆が遅れてもフォローできます。
しかし、数を増やしてしまうと、寝ずに書いても間に合わないという事態になりかねません。
連絡なしでの納期遅れは大幅に信用を失います。
そうならないように注意しましょう。
Webライターは納期以外に作業の束縛は多いのか?

Webライターは納期以外に作業に関してルールがあります。
しかし、束縛はそこまで多くないとぼく個人としては感じています。
また、ルールの数や重要度も依頼主によって大きく変わるので、一概に束縛が少ないともいえません。
もし、ルールが多すぎてやりづらいと感じるのであれば、その依頼主の依頼を受けなければいいだけの話です。
また、依頼をもらった後でも、できない旨を伝えればOK。
今後、その依頼主から依頼をもらうことはできませんが、依頼は星の数ほどあるのでそこまで気にする必要はないでしょう。
依頼主側も、初めて雇う外注ライターは飛ぶ可能性があることを考慮して外注しています。
あまり深刻に考える必要はありません。
Webライターとして依頼をもらう際のよくあるルール

Webライターの場合、個人ブログと違い相手がいて成り立つ仕事なので、当然、ある程度ルールがあります。
では、一般的によく提示されているルールを3つご紹介します。
マニュアルが用意されている
ライティングに関してのマニュアルが用意されている人も多いです。
マニュアルのルールはこれもまた、依頼主によって大きく変わります。
例えば、「車」という言葉は、「クルマ」とカタカナで表記する。
「。」では必ず改行するというような簡単なルールもあります。
それに対して「必ず1次情報を意識すること」。
どのサイトから見つけた情報なのかが分かるように、参考にしたサイトのURLを記事内に入れ込む。
具体的な数字をスペック表をもとに記載する。
「例」
・この車は小回りがきく→NG
・この車は最小回転半径が4.5mなので小回りがきく→OK
このように依頼主によっては、事細かなルールがある場合もあります。
その点は、依頼をもらわないと分からない部分です。
もし、めんどくさいルールが嫌なのであれば、マニュアルのない依頼主を探すようにしましょう。
納品後の著作権は依頼主に渡る
90%以上の依頼に当てはまることですが、Webライターとして書いた記事の著作権は、納品後に依頼主に渡ることがほとんどです。
著作権が渡ったからと言って、あなたが何かをする必要はありません。
しかし、納品後にSNSや自身のブログなどで、「この記事は自分が書いた」といってはいけません。
例外もあります。
記名記事であれば、納品後であっても著作権は自分自身にあり続けます。
そのため、堂々と「この記事は自分が書いたものだ」と提示することができるのです。
そんなにシビアになることではないですが、著作権は法律にも関わってくることなので注意しておきましょう。
納品方法
納品方法も依頼主によって違います。
例えば、記事を書いたワードファイルを送信するだけでいい場合もあります。
しかし、たくさんの外注ライターを雇っている場合、誰がどの記事を書いたのか分からなくなるため、スプレットシートで管理していることも。
自分の番号を振り分けられ、ファイル名に入れてほしいなどという納品方法もあったりします。
また、Wordファイルで納品するのではなく、Googleドキュメントで共有しなければならない場合もあったりと、依頼主によってまちまちです。
まとめ
このように、自分のブログを作るのとは違って、Webライターにはちょっとしたルールがあります。
今まで、自分独自で書いてきた方法とは違った書き方を要求されることもあります。
依頼をもらってからのルールや流れ、納期に関しては平均などはなく、本当に人それぞれです。
ただ、間違いなく言えることは、どの依頼主も上位表示を求めているということ、そしてWebライターという仕事は相手がいてはじめて成り立つ仕事であるということ。
その2つを理解しておけば、なぜこのマニュアルなのかがわかります。
またできないことはできないとはっきりと伝え、もし納期に遅れそうなら事前に連絡を入れる。
このような常識的なことがとても大切です。