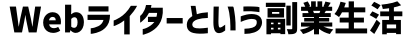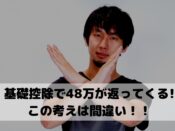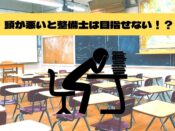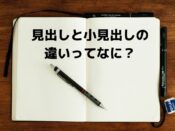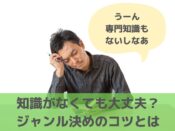週7でバイトの掛け持ちは労働基準法違反?副業でバイトをおすすめしない理由も
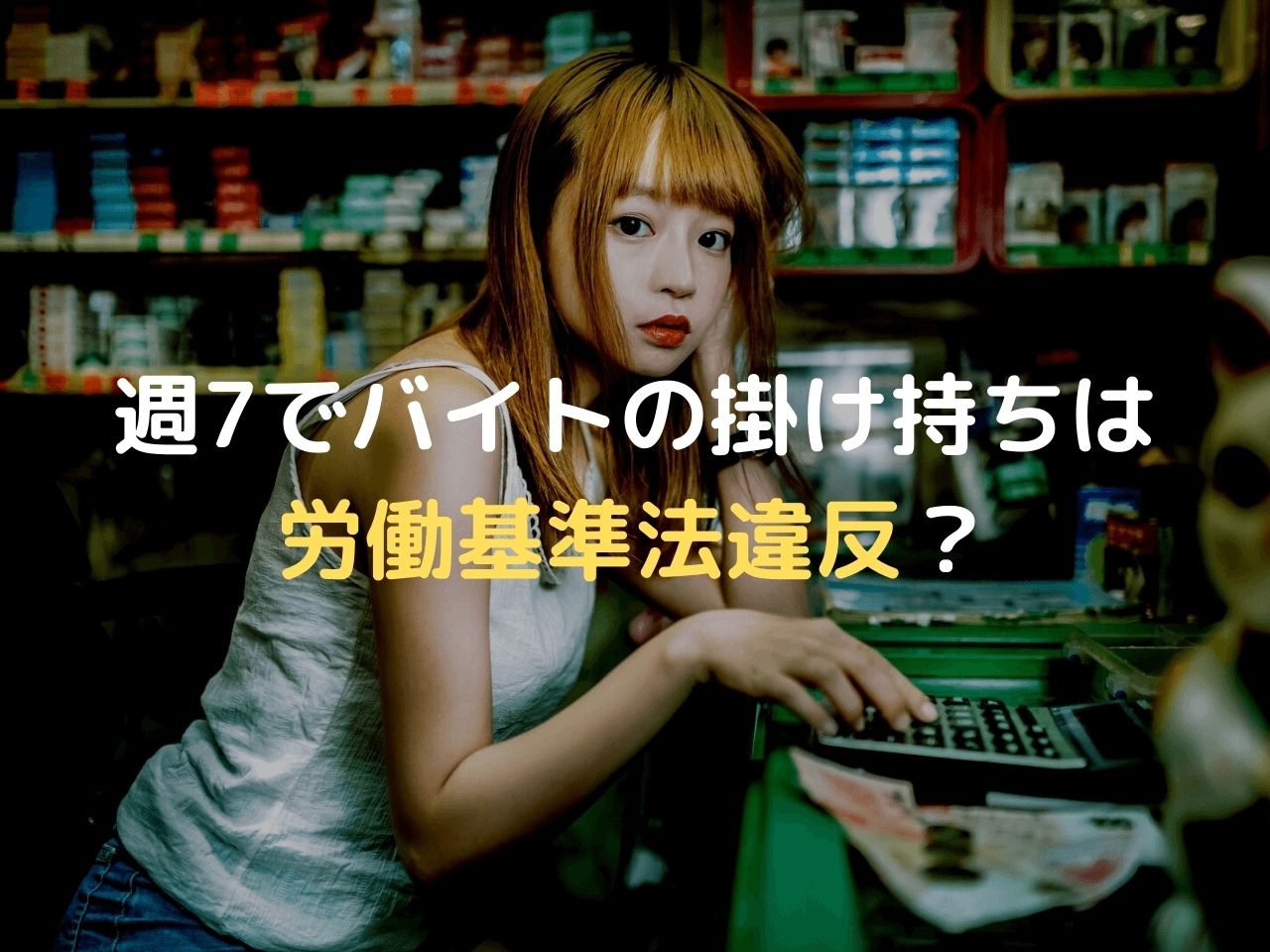
こんばんは!
ね・・・ねむい。
ブログも大変だなあ。
今日は副業のバイト掛け持ちについて書いていきます。
副業でアルバイトをしている方のなかには、週7でバイトをしている人もいるでしょう。
しかし、働き方の見直しによって、残業時間の取り決めが厳しくなりましたよね。
もしかすると、バイトをすることで、労働基準法違反になっているのではないかと思ってしまいます。
結論をいうと、労働基準法は労働者を雇用する使用者に向けた法律であり、労働者が労働基準法で定められた時間を故意に違反しても罰則などはないのです。
しかし、罰則対象になる可能性がある会社は、おそらくアルバイトとして雇ってはくれないでしょう。
そこで今回は、そもそも労働基準法とはどんな法律なのか、36協定や働き方改革によって、なぜアルバイトの掛け持ちがしづらくなったのかをお話ししていきます。
バイトの掛け持ち自体は問題ない

法律的に見ても、副業アルバイトの掛け持ちは問題ありません。
2つのバイトを掛け持ちしてようが、5つだろうが同じです。
仮に、本職で残業をしたあとに、バイトをしても大丈夫です。
しかし、最近では時間外労働は月100時間以内。
月45時間を超えるとややこしい提出物があるだとか、そういった話を聞きますよね。
週7でのバイトの掛け持ちで問題になる労働基準法とは?

時間外労働を決定している法律は「労働基準法」です。
労働基準法とは、本来弱い立場である労働者を、使用者から守ってくれている法律だと覚えておきましょう。
使用者は事業主とか会社を指します。
つまり、人を雇って働かせる側が使用者であり、使用者に雇われる側が労働者なのです。
労働基準法では労働に関する最低基準を定めています。
さまざまな決まりを定めていますが、最低賃金なども労働基準法で管理しています。
例えば、何時間働いても日当1000円などのような圧倒的に労働者に不利な状況になる場合、いくら契約書にサインをしていても無効です。
このように、私たち労働者は「労働基準法」により、不利な契約から守られています。
違反となる可能性のある部分は36協定
バイトの掛け持ちで問題となる可能性のある条例が36協定です。
36協定(サブロク)とは、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める、労働時間などの決まりを指します。
2019年に行われた働き方改革によって、36協定で定めている時間外労働に、時間の上限と罰則が追加されました。
36協定では、
という決まりがあります。
加えて、仮に特別な事情がある場合でも、
・年720時間
・複数月平均80時間以内
・月100時間未満
この3つの条件を超えることはできません。
つまり、無制限に時間外労働、いわゆる残業をさせるなよということです。
仮に、決まりを無視して残業させてしまうと、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が待っています。
そのためあらゆる会社が、2019年以降できるだけ残業をさせないように目を光らせているのです。
バイトの掛け持ちをして違反となるのは労働者じゃなく使用者

覚えていてほしいのは、労働基準法は使用者から労働者を守るために作られた法律だということ。
つまり時間外労働に関してお伝えすると、違反となるのは働いている労働者ではなく使用者なのです。
サービス残業もいまだに続いている悪しき習慣ですよね。
そのような会社は、働き方改革が始まったとき、なかなか働く環境を変えられてなかったんじゃないかと思います。
そして、働き方改革により社員の勤務時間を大幅に減らしたことで、仕事が全く回らなくなってしまった会社もあるでしょう。
このように、労働基準法や36協定は労働者の待遇を改善するために作られました。
仕事に支障がないならいくら働いてもよい
仮に、36協定に接触しそうなほど、バイトなどで仕事をしていても他の仕事に支障がなければ、全く問題ありません。
しかし、本職に影響が出てしまうと話は別です。
毎日深夜までバイトをしているから、正社員での仕事ではいつも集中力がなくミスが多い。
このように、本職に悪影響がある場合、会社側が副業を禁止することができます。
副業は国も容認している働き方だけど、あくまでも本職をきちんとしたうえで行いましょうとガイドラインにも書かれてあります。
そもそも、副業をはじめる場合、副業をしたから疲れている。
このような言い訳は通用しないことを理解しておく必要があります。
週7に限らず副業でアルバイトをおすすめしない理由

基本的にぼくのブログでは、副業としてアルバイトを選ぶことはおすすめしていません。
その理由は単純に、大きな金額は望めないのもありますし、場所や時間の拘束がもったいないと思うからです。
時間と場所に縛られると、それ以外の時間の使い方にも気を使わなければなりません。
また、移動時間が多ければ本当にもったいないですよね。
時間も場所も決まりがなければ、家に居ながら仕事ができます。
さらに、嫌な人と関わる必要がなく楽です。
ぼくがバイトをおすすめしないのは、このような理由があります。
働き方改革により副業アルバイトを受け入れてくれない会社も
バイトをおすすめしないのは働き方改革により、時間外労働の上限が決まったことで、副業アルバイトを受け入れてくれない会社も増えたからです。
厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、
労働者が、事業主を異にする複数の事業場において「労働法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。
参照:厚生労働省ガイドライン
と記載されています。
少し難しいので簡単に説明すると、「正社員の副業としてアルバイトをしても、アルバイトの時間は時間外労働として計算してね」ということです。
なにがいいたいかというと、社員が勝手に副業でアルバイトして、36協定で定められている時間より多く働いたとしても、会社側が罰則を受ける可能性があるということです。
そう考えると、正社員の会社は「聞いてない」で逃げ切れるかもしれません。
でもアルバイト先の会社は、アルバイトでも履歴書の提出などがあるので、正社員として働いていることを知ってますよね。
つまり、36協定の罰則の矛先は、アルバイトの会社に向かうのです。
たった1人のアルバイトのために、30万円もの罰則を払うのはアホらしいですよね。
そのため、副業でバイトをしたい場合、働き口を見つけることが難しくなります。
まとめ

週7でバイトの掛け持ちをしても、労働者側が罰則を受けることは考えづらいです。
労働基準法は、使用者に向けて作られた法律であり、いわば労働者を不公平な契約から守ってくれる、お守りのような役割があります。
そのため、正社員として働きながらバイトしても全く問題はありません。
しかし、雇う会社側は労働者が働きすぎると、労働基準法により裁かれる可能性もあります。
副業を容認している会社は徐々に増えています。
しかし、働き方が厳しくなった現代では、なかなかバイト先が見つからないということも多いのです。
そのような状態にならないよう、自分で稼ぐ力を身につけることをぼくはおすすめしています。
バイトもいいですが、労働ばかりで疲弊し倒れないように気を付けてくださいね。