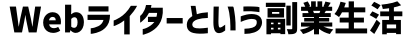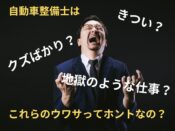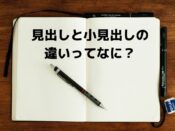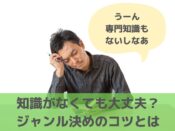整備士は減っているのか?実はあまり減ってない新事実を解説!

こんばんは。
最近、運動不足なんですよね。
でも、外走るの寒いし・・・って思いながらVoicyのながら日経聞いてたら、1日1分でも逆立ちをすると肩凝りとか、血流がよくなると聞きさっそく試しました(笑)
今日は、ほんとうに整備士は減っているのか?について書いていきます。
Twitterなんかでもよく、整備士は給料が安いからどんどん辞めている、という話なんかも聞きますよね。
でも、ほんとうはどうなのか、数値で見る機会はあんまりないんじゃないでしょうか。
わざわざ調べて確かめようと思う人も少ないんじゃないかなと。
そこで、ぼくがかわりに調べてみました。
そうすると、思っていた数値と違っていました。
調べた結果ですが、整備士の数って変化があまりなかったんです。
※もし表の見方間違ってるとか、調べた数値が違うなんてことがあればご指摘お願いします。
自分でグラフも作ってみたので、参考までに読んでいただけたら嬉しいです。
整備士になって整備士不足を実感した

ぼくはつい最近、整備士になった新参者ですが、整備士になってみて整備士不足を実感しました。
Twitterなんかでも、整備士が少ないとか言っていたり、安い給料明細のツイートがバズっていることなんてよくある話ですよね。
整備士の副業に関しての記事はこちらです。
実際、ぼくの店でも入庫が多くて手が回らないこともあります。
どこの店もそうだと思うんですが。
それでも、ぼくの店は整備士が多い方だと思っています。
アルバイト先の民間整備工場なんかも、3月の繁忙期なんかは毎日2時とかまで車検作業してますし。
そのくらい整備士が不足しているってことなんだと思います。
ぼくの同機は3人そのうち2人はベトナム人

ぼくと同時に入社した整備士はぼく以外で3人です。
そのうち2人はベトナム人。
しかも、ぼくの年は整備士免許を取得した人がいませんでした。
ぼくは中途なんで当然持ってません。
そしてもう一人の日本人は、整備とは全く関係ない大学卒。
営業に入ろうとしたところ、面接でメカニックにならないかと詰められたそうです。
2人のベトナム人は、整備士の専門学校は卒業しているものの、試験は不合格。
3度目だったかな?の挑戦でやっと受かってました。
そして、ぼくらが入社した次の年の整備士採用は1人だったようです。
正直、ぼくが働いている店って、大阪でも10店舗以上ある結構大きな店なんですが、そんな店ですら整備士の採用があまりない事実。
ほんとうに少ないんだなと実感しました。
ほんとうに整備士は減っているのかを調べてみた

整備士が減っているというウワサしか知らないので、ほんとうに減っているのかを調べてみました。
結果は、そんなに減っていないです。
参照したのは、日本自動車整備振興連合会のデータです。
平成22年度からの数値が出ていました。
いろんな数値が細かく出ていたんですが、全てを拾っても見づらくなるので、必要な部分だけを抜粋。
今回抜粋した数値は、
・整備関連従業員数
・整備要員数
・整備士数
この3つです。
なぜ3つも数値を拾ったのかというと、もしかすると、整備資格を持っている人だけ少なくて、その他の数値は変わってくるんじゃないかと思ったから。
おそらくですが、整備関連従業員数はかなり大きな括りで定義されていて、実際に整備をしていない人も含まれていると思います。
そして、整備要員数は資格の有無は関係ない整備担当者で、整備士数は実際に資格を持っている人。
このような区分だと思っています。
すいません、時間がなくて詳しく調べられてないです。
時間ができしだい、聞いて書きなおします。
数値的にはそんなに変わらない
数値的にそんなに変化がないと感じたので、グラフ化したらはっきりと現れました。
まず、整備関係従業員数ですが、このようなグラフになりました。
【整備関係従業員数】~平成22年度から令和2年度~
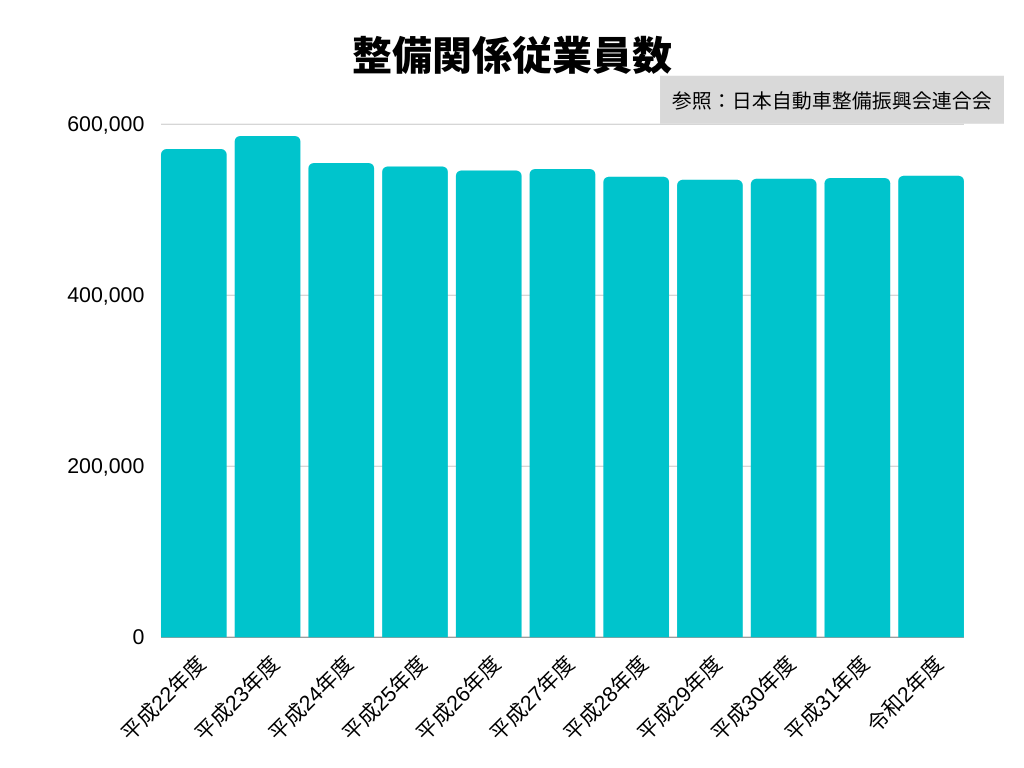
詳しい数値としては、平成22年度が約57万人に対し、令和2年度で約54万人。
3万人程度減ってはいますが、そこまで大打撃になる数値ではないかなと。
次に整備要員数です。
【整備要員数】~平成22年度から令和2年度~
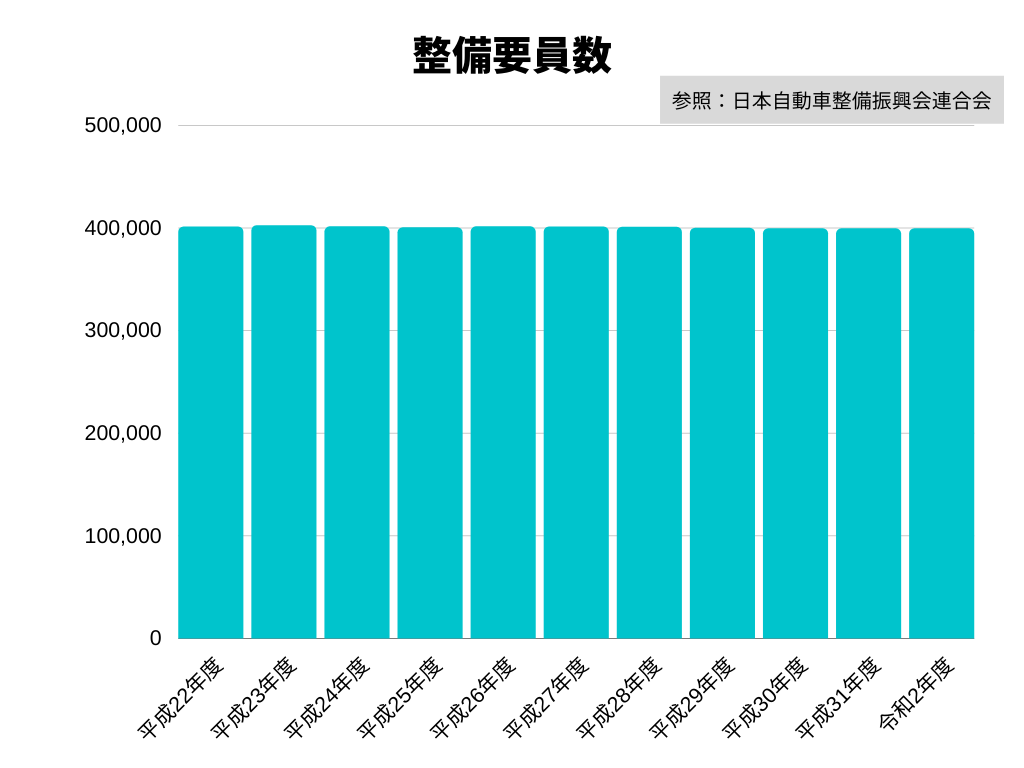
整備要員数は平成22年度で約40万1,000人。
そして、令和2年度でも約40万人とあまり変化はありません。
さいごに整備士数です。
【整備士数】~平成22年度から令和2年度~
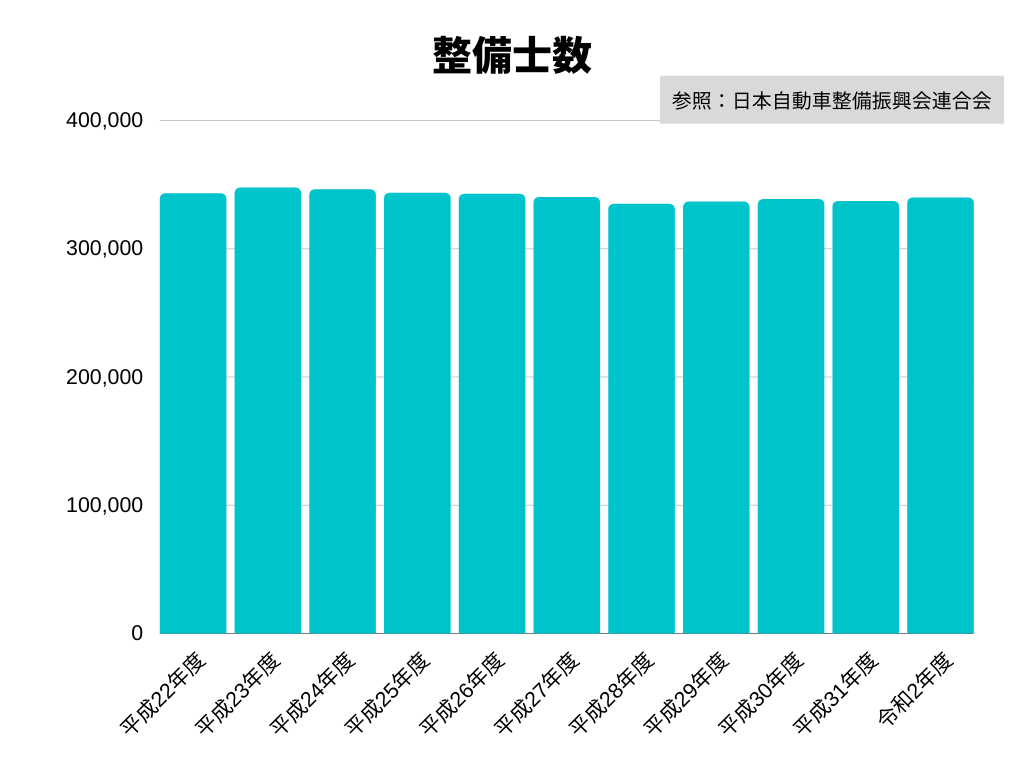
整備士数は平成22年度で約34万人。
令和2年度でも約34万人と、ほぼ水平という結果になりました。
この数値が必ずしも、リアルな現場を表しているわけじゃないと思います。
もしかすると、実際はもっと少ないとかもあるでしょう。
しかし大幅なずれはない、と個人的には考えています。
ではここで疑問が生まれますよね。
整備士の数に変化がないのに、なぜ整備士不足だといわれているのか?
実は、整備士不足といっているだけで、ほんとうは十分な数の整備士がいるんじゃないのか?
ぼくはこの疑問が浮かびました。
そこで、今度は自動車の普及率を調べてみたところ、原因が分かりました。
整備士不足の原因は自動車の普及にある

整備士不足の原因は車の普及率が原因でした。
整備士の数はほぼ変わっていないのに、車の数はずっと右肩上がりだという数値がはっきりと表れる形に。
参照したのは、こちらも同じく日本自動車整備振興連合会のデータです。
調べたデータは国土交通省でも使っていたのと同じなので、正確なデータだと分かります。
昭和41年からずっと右肩上がり
実際に自動車がどれだけ走っているのかを確認するために、「自動車保有台数の推移」を検索しました。
するとこんな結果に。
【乗用車保有台数】~昭和41年度から令和3年度~
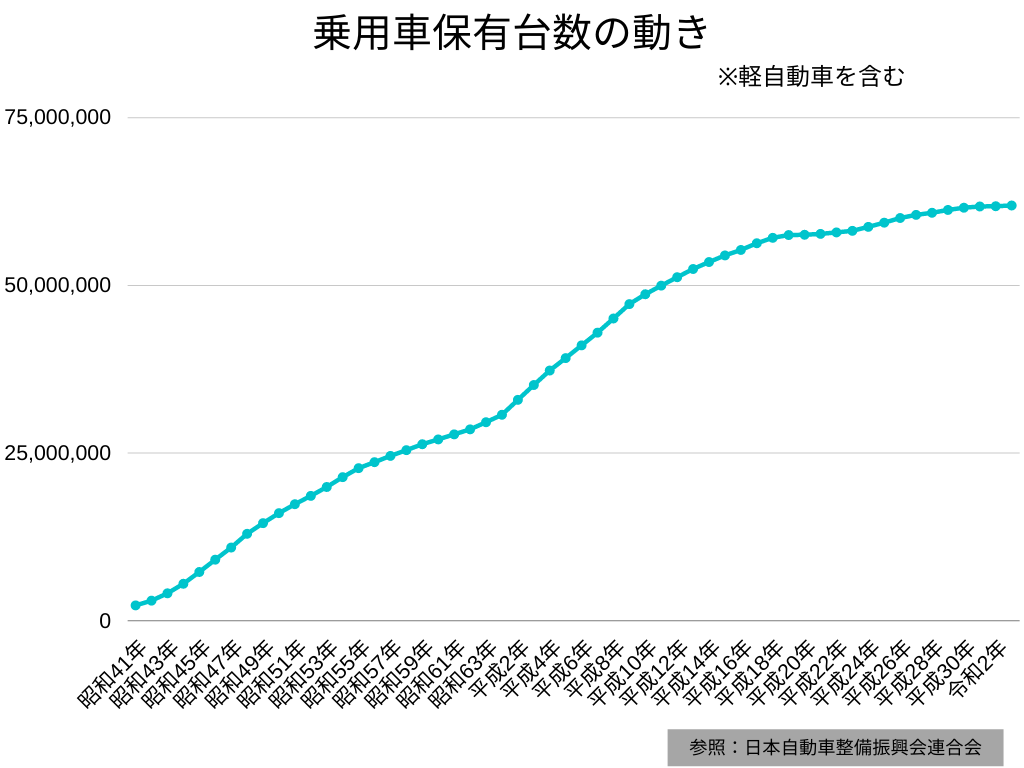
昭和41年からずっと右肩上がりなんですよね。
ぼくはこれを見て納得しました。
これは乗用車だけの数値ですが、乗用車の他に
・貨物車
・乗合車
・二輪車
・特殊用途車
この4つの数値も別途であります。
つまり、公道を走っている車の数はこの数値よりも多いんです。
そこで平成22年度から令和2年度だけに絞り、全ての合計のグラフを作りました。
【全自動車保有台数】~平成22年度から令和2年度~
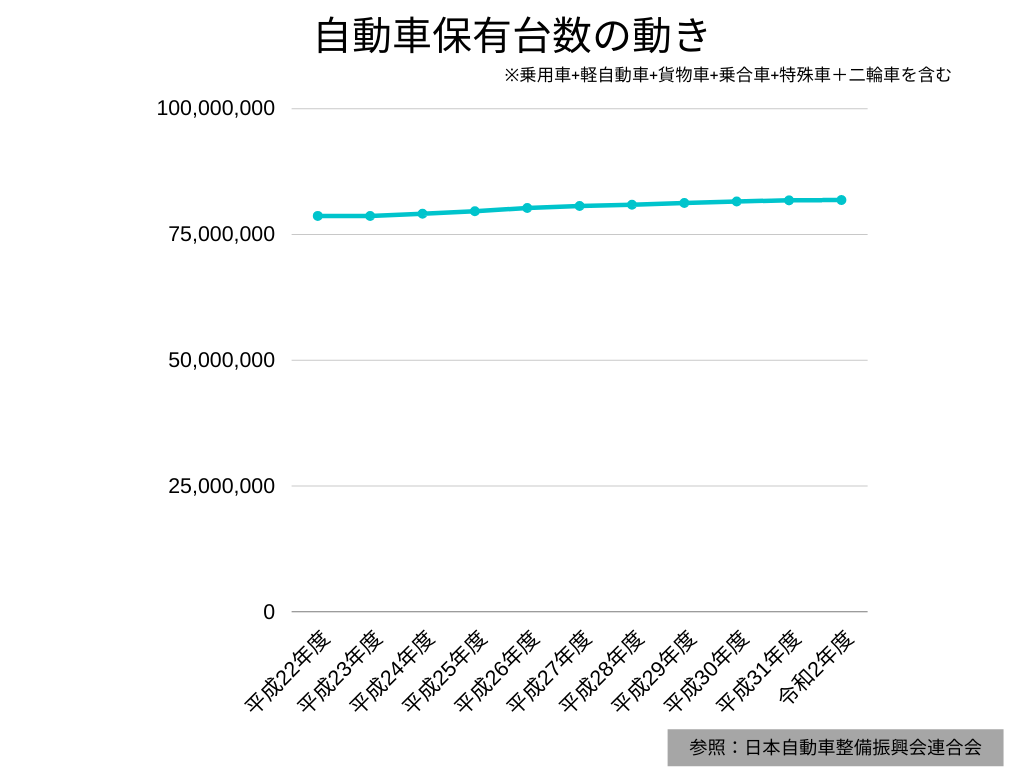
数字が多いので分かりづらいですが、平成22年度での保有台数は約7869万台なのに対し、令和2年度では8184万台まで増加しています。
単純計算で315万台分の車やバイクが増加しているということです。
それを同じ数の整備士で整備しなければならないので、人材不足になることが分かりますよね。
道路を走る車に対し整備士が少ないという事実

つまり、車は増加しているのに、整備士は増加してない、むしろちょっとずつ減っている事実があります。
これを見たとき、先輩の言葉を思い出しました。
「俺らのときは、丁寧に教えてはくれなかったけど、自分で考える時間があった。」
これは50代の先輩整備士が言っていた言葉です。
もちろん今も、ゼロではないですがその人達の時代より、少ないのでしょう。
今回調べたことが、整備士不足の大きな原因なんだなと納得しました。
先日書いた記事のように、将来、整備士があまりいらない時代がやってくるかもしれませんが、それは10年以上先の話だと考えています。
整備士の将来について書いた記事はこちらです。
今すべきなのは、次の世代を担う若い整備士を増やして教育すること。
それに尽きるのではないでしょうか。