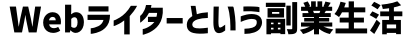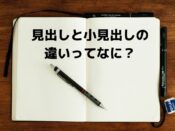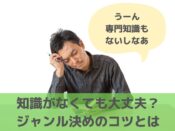日本は給料からの控除が多すぎるのか?金額の計算方法も

こんばんは!
本を読みたいんですが、読み始めると寝てしまう・・・。
どうすればいいですか?
今日は、給料の控除について書いていきたいと思います。
日本での控除金額が多すぎると思っている人も多いでしょう。
どこの国と比べているかによりますが、ぼく個人としては妥当な金額かなと思います。
しかし、基本給が低いとどうしても控除金額が多く、そして、引かれすぎているように感じてしまいますよね。
控除と一口にいっても、国が定めている控除と会社によって変わる控除の2種類があります。
そこで今回は、控除についての基礎知識と、いくら差し引かれるのが妥当金額なのかをご紹介します。
日本は給料からの控除金額が多すぎるのか?
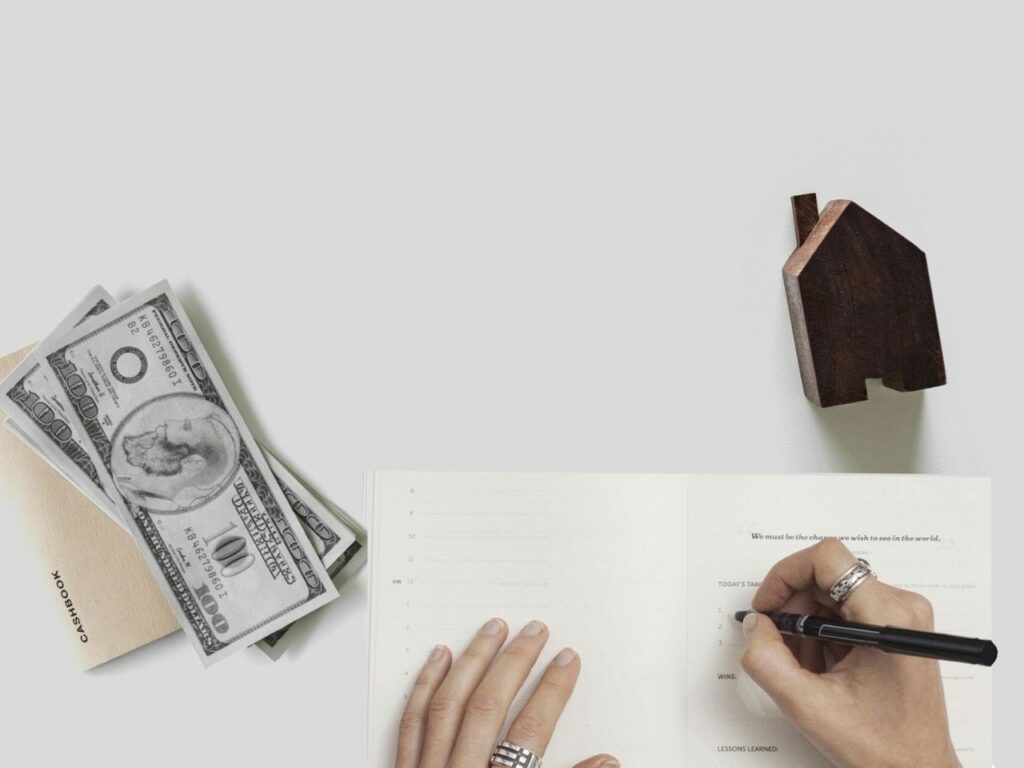
冒頭にも書きましたが、給料から天引きされている控除金額は妥当ではないかとぼく個人としてはそう考えます。
理由としては、控除ってそもそも保険料とか税金なんですよね。
控除の内容は、年金だったり健康保険料、社会保険など種類はさまざまです。
そして、日本はかなり安全な国でもあります。
その背景には、警察官がきちんと働いているとか、病院にいっても保険の範囲内であれば3割負担でいいとか。
そういったサービスというのは、税金や保険料からまかなわれています。
そして、公共のものとするのであれば、使った人使ってない人に関わらず、ある程度一律にしなければなりません。
そのため、若くても高い金額を支払う必要があるんですよね。
逆に、毎週病院通いの人は、きっと健康保険料は安いなって感じていると思います。
こういった、使っている人使っていない人の平均を出しているので、どうしてもサービスを受けていない人は、高すぎると考えてしまうのではないでしょうか。
そして、もし会社から必要以上に控除としてお金を払わされているのであれば、それに違法性があるのかを調べる必要があります。
そのため、まずは控除とはどういったものなのか、基本的な部分を理解しましょう。
会社を辞めるときには、ある程度、給料やその他の知識が必要になってきます。
会社を退職する場合に読んでもらいたい記事はこちらです。
税金などは控除という形で給料から金額を差し引いている
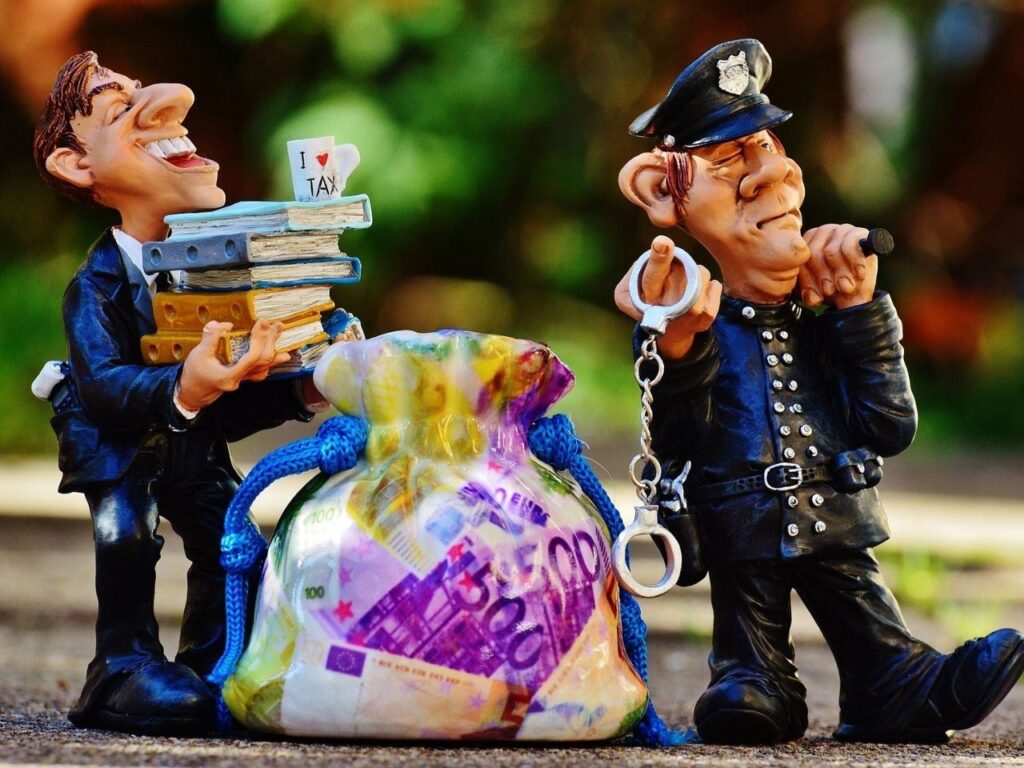
控除は、数量やお金を差し引くという意味を持ちます。
今回でいえば、税金に対しての控除なので、控除分は課税対象外だということです。
控除と一口にいってもその種類はさまざまですが、どの会社でも対象となっているものが保険や税金になります。
これらのお金は、控除という形で給料から差し引くことができるのです。
控除以外で会社への支払いがある場合、一度額面として給料を支払ってもらい、その後、社員から会社へお金を払う流れになります。
これらは労働基準法がベースとなっています。
労働基準法第24条では、
とされています。
少しわかりづらいですよね。
分かりやすく言い換えると、「会社は社員に原則として給料の全額を支払わなければならない。しかし、例外として控除としての天引きを認める」ということです。
つまり、例えば会社への支払いがあって、その金額を控除以外の方法で天引きするのはダメだよってことです。
そのため会社側は、控除以外の天引きを行えないのです。
もし、おかしな天引きがあるなら、それは違法かもしれません。
そのような場合、労働組合や厚生労働省が管理している「労働基準監督署」などへ相談しましょう。
控除は2種類に分かれる
控除は2種類に分けることができます。
そもそも、控除とは非課税となる支払い料金の総称です。
内訳はたくさんあります。
そのなかでも、国が定めている控除と会社が定めていない控除があるのです。
それぞれの名称は以下のとおりです。
- 法定控除
- その他控除
法定控除は国が定めている強制力を持つ控除。
それに対し、その他控除は会社ごとで控除内容が変わります。
それぞれの詳細は後述しますが、まず控除のカテゴリは2種類あると覚えておきましょう。
手取り金額の計算方法
控除内容の説明の前に、少しだけ手取り金額の計算方法をご説明します。
すごく簡単なんですが、給料明細の手取り金額しか見てない人もいます。
一体いくらもらっていていくら差し引かれているのかを理解していないと、給料が本当に安いのかどうか分からないですよね。
手取り金額の計算方法は以下のとおりです。
簡単ですね。
控除とは給料からの天引きなので、手元にお金が入ってくる前にすでに差し引かれています。
わざわざ自分で支払う手間が省ける分、いくらもらっていていくら支払っているのかきちんと理解しておく必要があります。
法定控除一覧や料金の計算方法など

法定控除とは、社会保険や健康保険など、国が管理している控除内容です。
一覧を表で載せておきますので、一度目を通してみてください。
| 控除の種類 | 内容 | 計算方法 |
| 健康保険料 | 病院での支払いに使用 | 給与額(賞与額)X健康保険料率=健康保険料 |
| 雇用保険料 | 失業した際に使用 | 給与額(賞与額)X雇用保険料率 |
| 厚生年金保険料 | 定年後に支給 | 給与額(賞与額)X18.3%=厚生年金保険料 |
| 所得税 | 所得に発生する税金 | 課税対象額X税率ー控除額=所得税 |
| 住民税 | 住んでいる場所に発生する税金 | 課税対象額X10%+均等割り=住民税 |
健康保険料
健康保険料は、病院での支払いの際に使う保険を指します。
保険者は会社が所属する健康保険団体です。
そして、保険料の半額を会社が負担してくれます。
【計算方法】
給与額(賞与額)X健康保険料率=健康保険料
地域や前年の年収、保険加入人数などで金額が変わりまた、40歳以上であれば健康保険料に介護保険料もプラスされます。
年齢によって保険料も変わるので覚えておきましょう。
雇用保険料
雇用保険とは、失業したときのためにかけておかなければならない強制保険です。
失業手当はもちろん、職業訓練を受けるときなどにも活躍します。
一定の期間保険に加入していなければ、失業保険は受け取れません。
【計算方法】
給与額(賞与額)X雇用保険料率
ちなみに令和3年の雇用保険料率はこのようになっています。
令和4年度に関しては、引き上げが決まったもののまだ、公式には発表されていません。
厚生年金保険料
厚生年金とは、国民年金に上乗せしてかける年金の一種です。
その他にも確定拠出型年金など、企業によって追加でかけている年金は違います。
国民年金より金額は高く設定されているものの、会社と折半でかけられるので支払金額は本来の保険料より安く設定されています。
厚生年金の金額は、月の報酬額や賞与(ボーナス)に18.3%をかけた額です。
【計算方法】
給与額(賞与額)X18.3%=厚生年金保険料
所得税
国が管理している、所得に関して発生する税金です。
所得金額が大きくなればなるほど、税率も上がっていきます。
そして、昨年の年収に対して金額が確定するので、会社員であれば源泉徴収という形で年収を予測しあらかじめ所得税を支払っている形となります。
そのため、払いすぎた所得税に関しては年末調整で戻ってくる可能性も。
【計算方法】
課税対象額X税率ー控除額=所得税
税率や控除額に関しては国税庁のHPに記載されています。
住民税
各都道府県や市町村が担当する、住んでいる地域を管理するための税金です。
こちらも、所得金額に比例して金額が変わります。
大前提として覚えておいてほしいのは、住民税には
- 均等割り(一律の金額で住んでいる地域によって変わる)
- 所得割税率(都道府県と市区町村で税率が変わり、合計10%になる)
この2つがあるということです。
【計算方法】
課税対象額X10%+均等割り=住民税
このような流れとなります。
※課税対象額の計算方法は以下のとおりです。
年収ー控除金額=課税対象額
所得控除額は扶養人数や年収などその人の環境によって控除割合が変わるので、その部分も計算する必要があります。
この記事では詳細は省略します。
その他控除は会社によってまちまち

その他の控除は会社によってまちまちです。
多くの会社で控除されている内容はこのようなものではないでしょうか。
- 組合費
- 社宅家賃
- 財形貯蓄
- 生命保険
その他控除では、国で定められている最低限の控除以外を指します。
つまり、この項目の控除は国が決めているのではなく、会社が取り決めた控除内容だということです。
そして、会社によって控除金額や項目が全く違います。
例えば、社宅に住んでいるなら社宅家賃という形で、給料から社宅の賃料が天引きされているはずです。
また、労働組合のある会社であれば、毎月組合費が引かれているなど。
また、社員旅行を毎年行っているなら、旅行費積み立てなどが追加されている可能性も。
このように、会社によって控除金額や項目が変わるので、一度確認してみましょう。
よく分からない控除がある場合は労使協定を確認
よく分からない控除がある場合、労使協定を確認することで把握できます。
その他控除は会社によって変わるものの、必要でないものを給料から天引きする行為は労働基準法違反です。
必要な控除なのか、不要な控除なのかを決めているルールが労使協定です。
労使協定(36協定)とは労働者(雇われ側)と使用者(雇い主)の間で交わされる協定を指します。
個人間で交わされるのではなく、例えば労働組合がいるなら、労働組合の代表者と会社側が書面契約をすることで協定が成立します。
この協定にも限度はあるものの、労働基準法では対応できない部分を労使協定で補っていると考えておきましょう。
しかし、あまりにもおかしな控除がある場合、一度労使協定を確認してみることをおすすめします。
労使協定は、就業規則と同じように社員の目の届く場所に保管しなければならないという決まりがあります。
また、労働組合のない会社の場合、この部分がおざなりになっていることもあるでしょう。
自分の給料からなにが天引きされているのかを知るのは、労働者の権利です。
手取りが低いと思うのであれば、その点もきちんと確認しておきましょう。
控除額が多ければ基本給が高くても手取り金額は低くなる

当然ですが、控除額が多ければ基本給が高くても手取り金額は低くなります。
例えば、社宅暮らしの人で社宅の賃金を給料から差し引かれているなら、手取り金額が安くなるのは当たり前ですよね。
また旅行費用積立金など、会社によって違う部分も多いです。
また整備士の場合、車のローンや保険代を給料から天引きされている人もいますよね。
しかし、これらの控除は本来もらった給料から支払う金額を、あらかじめ差し引かれているだけです。
そのため控除額が多い=給料が少ないという単純な話ではありません。
社宅家賃を支払っているなら生活するうえで家賃代は発生しない、車のローンを控除されているなら別途で車代は発生してないということです。
また、給料が安いと感じるもう一つの要因は、基本給をギリギリまで下げ、資格手当として手取り金額を上げることでボーナス代を極限まで下げるという方法です。
ぼくが以前働いていた会社は、こうして年収を下げる努力をしていました。(笑)
こんな会社は意外と多いと思います。
そのため、控除内容と一緒に、基本給などの収入面もきちんと確認しておきましょう。
まとめ

今回は、給料の控除に関しての記事を書きました。
なぜこの記事を書こうかと思ったかというと、Twitterで安い給料明細を公開してる人を何度も見たからです。
そのなかで結構な控除額がある人を見たことがあって、この記事を書こうと思いました。
基本給は18万くらいあったのに、手取りは12万くらいだったのかな?
なんでこんなに控除額があるんだろうと思いました。
加えて、自分の給料なのに詳細を知らない人が、かなりの数いるなと感じたからというのもあります。
「給料安い!」
「手当もほとんどない!」
こういっている人に
「基本給いくらなんですか?」
「手当いくらもらっているんですか?」
こんな質問をしても「給料明細見てないからわからん」って返事が返って来たりします。
文句を言う前に、自分が今どんな状態なのかを把握するのは当たり前だと思います。
そのうえで、基本給が少ない!とか、控除額が多すぎるとかの文句をいわないと全く前に進まないなと思います。
また、転職したとしても同じことの繰り返しになる可能性もありますよね。
そのため、文句が出てしまう気持ちは分かるんですが、まず、自分が今どんな状態なのか、あといくらほしいのかを明確にしてほしいです。
そうすると、どうすれば問題が解決できるのかが見えてくるんじゃないかと思います。
たった一度の人生です。
文句ばかり吐きだして年をとるのはもったいない!
後悔しないように行動していきましょう!